「スクリーニング検査」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。健康診断やがん検診で行われる検査の多くがスクリーニング検査に該当します。病気の早期発見には欠かせない検査ですが、正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。
本記事では、スクリーニング検査の定義や目的、わかること、利点、注意点について詳しく解説します。健康管理に関心がある方、がん検診や特定健診を受けようか迷っている方、検査結果の意味を正しく知りたい方は参考にしてみてください。
目次
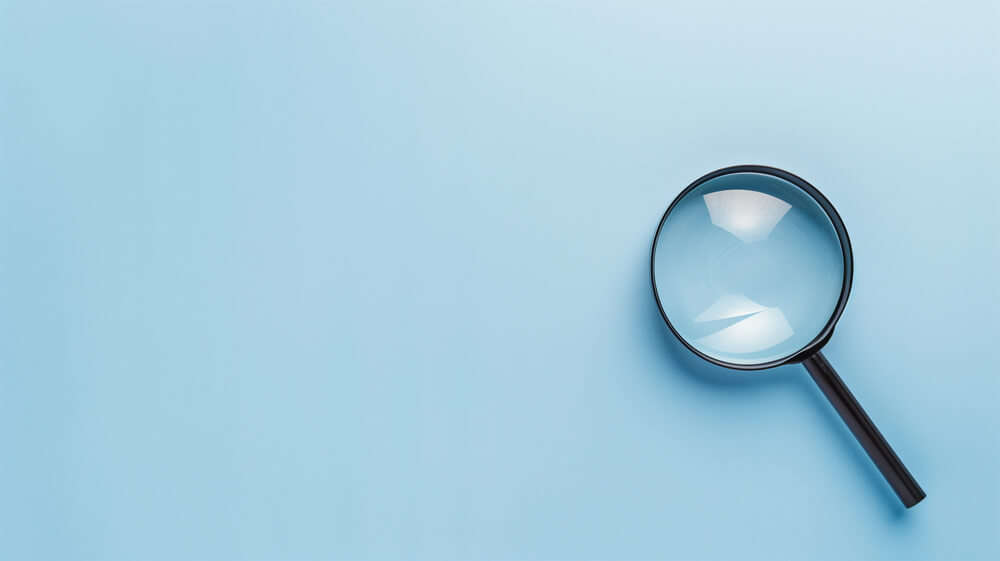
スクリーニング検査とは、自覚症状がない健康な集団を対象に、特定の疾患やそのリスクをふるい分け(選別)する目的で行われる検査です。臨床の場で症状のある人に対して行う「診断のための検査」とは性質が異なります。
病院で医師が患者の訴えに基づいて行う検査は、すでに何らかの症状や異常がある前提で、病気を確定するために実施されます。一方、スクリーニング検査は公衆衛生的な観点から、多くの人を対象に実施される点が特徴です。
スクリーニング(screening)は「ふるい分け」を意味する言葉です。一見健康に見える集団の中から、特定の疾患に罹患している可能性が高い人や、将来発症するリスクが高い人を効率的に見つけ出すために行われます。
たとえば、がん検診では症状のない段階で異常を発見し、精密検査につなげます。健康診断では血液検査や尿検査を通じて、生活習慣病のリスクが高い人を早期に把握できます。スクリーニング検査は「全員を精密に調べる」のではなく、「リスクの高い人を効率よく選び出す」ための第一段階として機能します。
スクリーニング検査の最大の目的は、早期発見・早期治療による予後の改善にあります。病気は進行してから見つかると治療が困難になり、身体的・経済的負担も大きくなります。早い段階で異常を発見できれば、治療の選択肢が広がり、完治の可能性も高まります。
また、妊婦に対して行う胎児スクリーニングも重要な検査の一つです。超音波検査などを通じて、胎児の発育状態や先天性の異常の有無を確認します。早期に異常を把握することで、出産前後の医療体制を整え、母子の安全を守る準備ができます。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/001132577.pdf

スクリーニング検査を受けると、検査結果から自身の健康状態についてさまざまな情報を得られます。主にわかることは、以下のとおりです。
それぞれ説明します。
スクリーニング検査では、現在特定の疾患にかかっている可能性を示す異常値や所見が発見されます。たとえば、便潜血検査で陽性となれば大腸がんの疑いが、胸部X線検査で影が見つかれば肺がんの可能性が考えられます。
ただし、スクリーニング検査の結果だけでは病気の確定診断はできません。異常が見つかった場合は、精密検査を受けて詳しく調べる必要があります。検査の段階では「病気の疑いがある」という情報が得られるにとどまります。
スクリーニング検査は、将来病気を発症しやすいかどうかの指標を示します。たとえば、特定健康診査では血圧、血糖値、脂質などを測定し、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病のリスクを評価できます。
検査値が基準値を超えていれば、生活習慣の改善や医療機関での治療が必要になる可能性があります。リスクを早期に把握することで、病気の発症を未然に防ぐための対策を講じられます。
スクリーニング検査を受けることで、自身の身体の現状を客観的に把握できます。自覚症状がなくても、検査結果から潜在的な問題が明らかになるケースは少なくありません。
定期的に検査を受ければ、数値の変化を追跡でき、健康状態の推移を確認できます。異常がない場合でも、現在の健康が維持されていることを確認する意味で価値があります。

スクリーニング検査の最大のメリットは、症状が出る前の段階で病気やそのリスクを発見し、人々の命と健康を守る「予防効果」を発揮する点にあります。具体的な利点は以下のとおりです。
それぞれ説明します。
がん検診などでは、症状が出る前に早期の段階で病変を見つけられるため、治療が成功する可能性が高まります。多くのがんは早期に発見されれば5年生存率が大幅に向上します。
たとえば、大腸がんは早期発見によって90%以上の5年生存率が期待できますが、進行してから見つかると生存率は低下します。スクリーニング検査による早期発見は、救命率を高め、死亡率を減少させる効果があります。
早期に発見されたがんは、進行がんに比べて手術範囲が小さくて済んだり、内視鏡治療など体への負担が少ない(低侵襲な)治療法で済んだりする場合が多くなります。入院期間も短く、治療後の回復も早いため、日常生活への復帰がスムーズです。
また、治療費も進行がんに比べて大幅に抑えられます。進行がんでは手術だけでなく抗がん剤治療や放射線治療が長期にわたる場合もあり、医療費が高額になります。早期発見による治療は、身体的にも経済的にも負担を軽減できます。
スクリーニング検査では、病気になる前の段階である「前がん病変」を発見し、治療することで病気そのものの発症を防げます。子宮頸がん検診では「異形成」、大腸がん検診では「腺腫(ポリープ)」など、将来がんに進行する可能性のある病変を早期に発見できます。
ポリープを切除すれば、大腸がんの発症リスクを大きく下げられます。病気になる前に対処できるのは、スクリーニング検査の大きな強みです。
検査結果が「異常なし」であった場合、多くの人は現在の健康状態について安心感が得られ、質の高い日常生活を送る助けになります。不安を抱えたまま過ごすよりも、定期的に検査を受けて健康を確認したほうが、精神的な負担は軽減されます。
また、異常が見つかった場合でも、早期に対処できることがわかれば、前向きに治療に取り組めるでしょう。
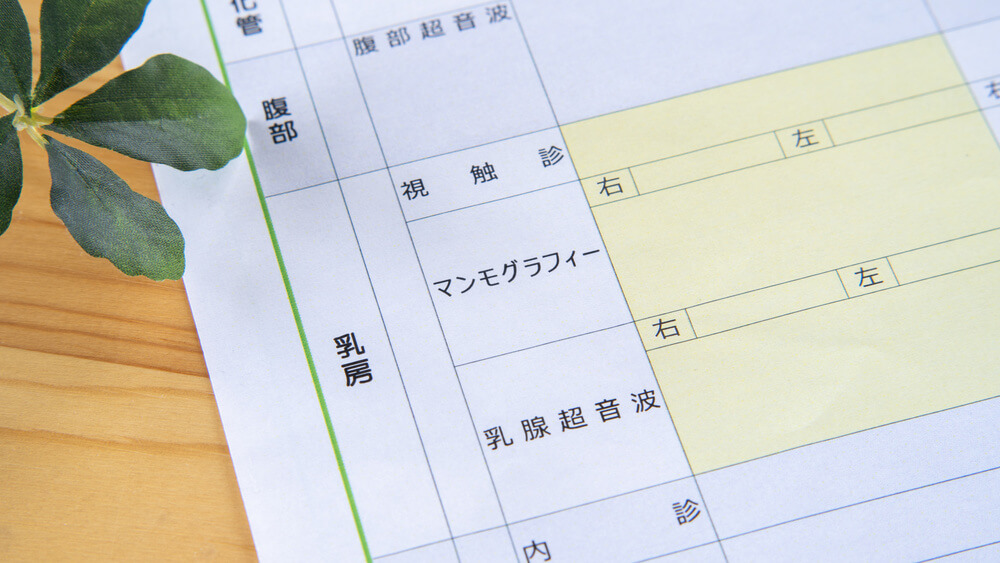
スクリーニング検査にはさまざまな種類があります。代表的な検査として、がん検診と特定健康診査について説明します。
がん検診は、特定のがんを早期に発見するために行われるスクリーニング検査です。日本では、国や自治体が推奨する「対策型がん検診」として、以下の5つのがん検診が実施されています。
| がんの種類 | スクリーニング検査の内容 | 主な対象者 |
| 大腸がん | 便潜血検査 (2日間の便に血液が混ざっていないかを調べる) | 40歳以上 |
| 胃がん | 胃部X線検査(バリウム検査) または 胃内視鏡検査(胃カメラ) | 50歳以上 (内視鏡は2年に1回) |
| 肺がん | 胸部X線検査 および 喀痰(かくたん)細胞診 (重喫煙者などハイリスク者に実施) | 40歳以上 |
| 乳がん (女性) | 乳房X線検査(マンモグラフィ) | 40歳以上 (2年に1回) |
| 子宮頸がん (女性) | 子宮頸部の細胞診 (子宮の入り口付近の細胞を採取) | 20歳以上 (2年に1回) |
がん検診は、各がんの特性に応じた検査方法が選ばれています。
胃がん検診ではバリウムを飲んでX線撮影を行う方法と、内視鏡で直接胃の内部を観察する方法があります。肺がん検診では胸部X線検査が基本ですが、喫煙歴のある人には痰の中のがん細胞を調べる喀痰細胞診も実施されます。乳がん検診のマンモグラフィは、乳房を圧迫してX線撮影を行う検査です。子宮頸がん検診は、子宮の入り口部分から細胞を採取して異常がないか調べます。
特定健康診査は、40歳から74歳までを対象に、メタボリックシンドロームとその予備群を発見し、生活習慣病を予防する目的で実施される検査です。通称「メタボ健診」とも呼ばれます。
内臓脂肪の蓄積に高血圧、高血糖、脂質異常が重なると、動脈硬化が進行し、脳卒中や心筋梗塞などの重大な疾患のリスクが高まります。特定健診では以下の項目を検査します。
| 検査項目 | 対象疾患・わかること |
| 身体計測 | 肥満度(BMI)、腹囲測定 (内臓脂肪の蓄積=メタボリックシンドロームのリスク) |
| 血圧測定 | 高血圧 (脳卒中や心臓病のリスク) |
| 血中脂質検査 | 脂質異常症(中性脂肪、HDL・LDLコレステロール)(動脈硬化のリスク) |
| 血糖検査 | 高血糖、糖尿病(空腹時血糖、HbA1c)(合併症のリスク) |
| 肝機能検査 | 肝機能障害(AST, ALT, γ-GTP)(脂肪肝や肝炎のリスク) |
| 尿検査 | 尿糖、尿蛋白 (糖尿病や腎臓病のリスク) |
特定健診の結果、メタボリックシンドロームやその予備群と判定された場合は、特定保健指導を受けられます。保健指導では、管理栄養士や保健師などの専門家から生活習慣改善のアドバイスを受け、食事や運動の見直しをサポートしてもらえます。

スクリーニング検査には多くの利点がある一方で、いくつか注意すべき点もあります。スクリーニング検査の結果が「陽性」や「要精密検査」であっても、病気の「疑い」があるというサインであり、病気の確定診断ではありません。必ず指示された医療機関で精密検査を受け、確定診断を得る必要があります。
主な注意点は、以下のとおりです。
それぞれ説明します。
偽陽性とは、実際には病気がない(陰性)にもかかわらず、検査結果が「陽性」または「要精密検査」と判定されてしまう状況を指します。
たとえば、便潜血検査では痔や大腸の良性ポリープからの出血でも陽性となる場合があります。マンモグラフィでは、乳腺の密度が高い若い女性で異常が疑われやすくなります。偽陽性が出ると、精密検査の結果が出るまでの間、病気かもしれないという強い不安やストレスを感じます。
また、本来不要な精密検査(内視鏡、生検など)を受ける必要が生じ、費用や時間、身体への負担が伴います。
偽陰性とは、実際には病気がある(陽性)にもかかわらず、検査結果が「異常なし」と判定されてしまう状況です。がんは発生初期には小さすぎて見つけられない場合や、検査方法によっては検出が難しい場所にある場合があるため、偽陰性は完全にゼロにはできません。
偽陰性が起きると、病気が見逃されたことによる安心感から、自覚症状が現れるのが遅れ、結果的に病気の発見・治療が遅れてしまう可能性があります。スクリーニング検査で異常なしと判定されても、定期的に検査を受け続けること、気になる症状があればすぐに医療機関を受診することが大切です。
過剰診断とは、治療をしなくても寿命や健康に影響を及ぼさない、進行が極めて遅い病変(がんなど)をスクリーニング検査で発見してしまう状況を指します。病変が将来進行しないものであったとしても、現在の医療では安全のために治療(手術など)が行われるケースが多く、本来不要な身体的・心理的・経済的負担を負う結果になります。
たとえば、前立腺がんや甲状腺がんの一部は進行が非常に遅く、生涯にわたって症状を起こさない場合があります。過剰診断は検査技術の向上によって増加傾向にあり、医療界でも議論が続いています。

近年注目されているのが、だ液を用いたがんリスク検査です。従来のがん検診と比較して、受診率の向上と被検者(受ける人)の負担軽減という課題を克服できる点に優位性があります。
第一に、身体的負担の少なさが挙げられます。採血や内視鏡検査が苦手な人でも、だ液を採取するだけで複数のがんのリスクを同時にチェックできます。痛みや不快感がないため、検査へのハードルが大幅に下がります。
第二に、検査が簡便で短時間で済む点です。専用の容器にだ液を入れるだけで検査が完了します。医療機関での拘束時間が短く、忙しい人でも受けやすい検査です。
そして第三に、心理的ハードルの低さがあります。内視鏡やマンモグラフィのような身体への侵襲がないため、「検査が怖い」「恥ずかしい」といった理由で検査を避けていた人にとって、受けやすい選択肢となります。
だ液によるがんリスク検査は、膵臓がん、肺がん、大腸がん、乳がん、口腔がんなど、複数のがんのリスクを一度に評価できます。定期的に検査を受けることで、がんの早期発見につながる可能性が高まります。

スクリーニング検査はあくまで「ふるい分け」であり、目的を果たすための次のステップが必須です。検査結果が「高リスク」だった場合でも、すぐに病気だと確定したわけではありません。冷静に次の行動を取りましょう。
高リスクと判定された部位(大腸、乳房、膵臓など)の専門医や、総合的な人間ドックを提供している医療機関を受診します。検査結果を持参し、医師に相談しましょう。かかりつけ医がいる場合は、まずかかりつけ医に相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらう方法もあります。
確定診断のために、スクリーニング検査よりも精度の高い、専門的な検査を受けます。たとえば、便潜血検査で陽性となった場合は大腸内視鏡検査を、マンモグラフィで異常が見つかった場合は超音波検査や生検を行います。精密検査では、病変の有無、大きさ、性質などを詳しく調べます。
精密検査の結果、本当に病気であれば、早期治療を開始します。早期発見であれば治療の選択肢が広がり、身体への負担も軽減できます。一方、精密検査で異常が見つからなければ、偽陽性だったと判明します。この場合も、定期的にスクリーニング検査を受け続けて健康状態を見守ることが大切です。
スクリーニング検査は、自覚症状のない段階で病気やそのリスクをふるい分け、早期発見・早期治療につなげるための重要な検査です。早期発見による救命効果、身体的・経済的負担の軽減、病気の発症予防、精神的な安心感の獲得など、多くの利点があります。一方で、偽陽性や偽陰性、過剰診断といった限界も理解しておく必要があります。
がん検診や特定健康診査といった従来のスクリーニング検査に加えて、だ液によるがんリスク検査は、身体的・心理的負担が少なく、複数のがんを同時にチェックできる優れた選択肢です。サリバチェッカーは、一度のだ液摂取で6種(男性5種)のがんを同時に調べられます。日々の健康管理と早期発見のための強力なツールとして、定期的な受検をおすすめします。