ウイルス感染が原因となる肝炎には、B型肝炎やC型肝炎などがあります。なかでもC型肝炎は、初期では自覚症状がほとんどないまま進行することが多く、気づかないうちに肝硬変や肝がんに至るケースも珍しくありません。
しかし、近年は治療法が大きく進歩し、C型肝炎は適切な治療を受ければウイルスを体内から排除できる病気となっています。だからこそ、早期に感染に気づき適切に対処することが、将来の健康を守るための第一歩になります。
この記事では、C型肝炎の初期症状や感染経路、検査の方法、最新の治療法などについて、専門的な内容をわかりやすく解説します。
目次
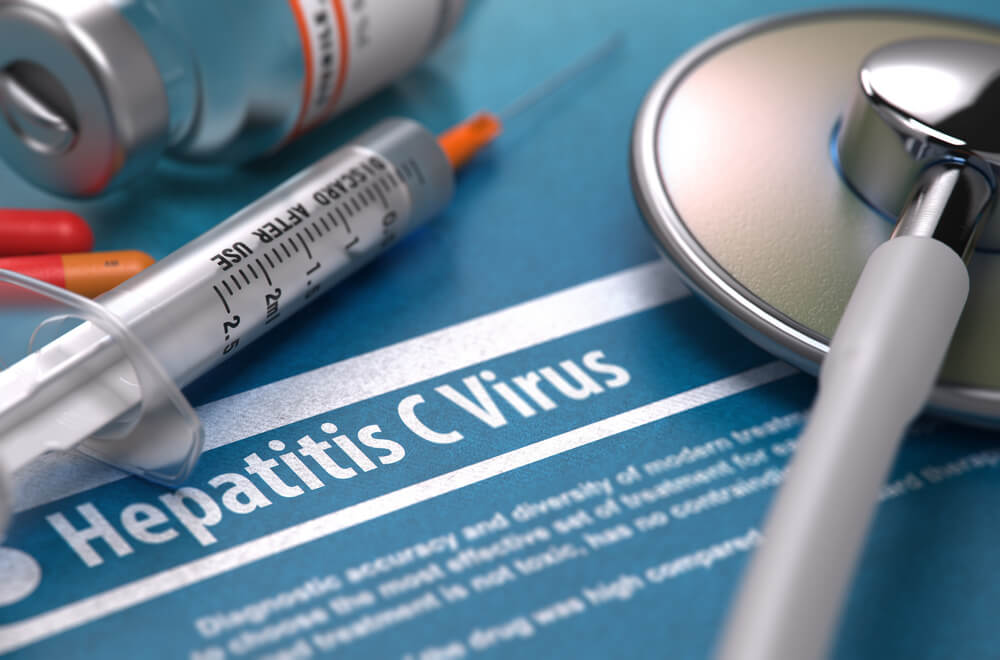
C型肝炎は、C型肝炎ウイルス(HCV)に感染することで発症する肝臓の病気です。ウイルスが肝臓の細胞に侵入して増殖することで、細胞が破壊され、炎症(肝炎)が起こります。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど自覚症状があらわれにくい臓器で、C型肝炎も気づかないうちに進行することがあります。治療せずに放置すると、肝硬変や肝がんへと進行するおそれがあるため、早期発見・早期治療が非常に重要です。
かつては、輸血や注射器の使い回しなどが原因でC型肝炎に感染するケースが多く報告され、とくに40歳以上の世代に多くみられました。現在は感染対策が強化され、新たな感染者数は減少傾向にあります。
しかし、抗ウイルス療法が進歩した現在でも、年間約2万3千人が肝がんで命を落としており、肝がん患者のおよそ半数がHCV抗体陽性であることから、C型肝炎は今もなお深刻な健康問題とされています。
ウイルス性肝炎にはいくつかの種類がありますが、なかでもC型肝炎とB型肝炎は慢性肝炎の主な原因として知られています。どちらも放置すれば肝硬変や肝がんといった重大な病気へ進行するリスクが高いため、国を挙げた感染対策が行われています。
C型肝炎とB型肝炎はどちらもウイルスが原因ですが、感染経路や経過、治療法などに違いがあります。
| C型肝炎 | B型肝炎 | |
| 原因ウイルス | C型肝炎ウイルス(HCV) | B型肝炎ウイルス(HBV) |
| 主な感染経路 | 血液感染(血液製剤、医療行為など) | 血液・体液を介した感染 (母子感染、家庭内感染、医療行為、性感染など) |
| 病気の経過(感染の持続) | 年齢に関わらず約70%で感染が持続する(キャリア化)ゆるやかに症状が進行し、慢性肝炎を発症することが多い | 乳幼児期までの感染は約90%以上で感染が持続する(キャリア化)約90%は無症状のまま経過する |
| 治療法(抗ウイルス療法) | 内服薬でウイルスを排除する注射薬で肝臓の炎症を抑える | 内服薬でウイルスの増殖を抑える注射薬で肝臓の炎症を抑える |
| ウイルス再活性化のリスク | 排除後は再活性化のリスクは低い | 免疫抑制剤や化学療法の使用でウイルスが再び増殖することがある |
| ワクチン | なし | あり(1歳までの定期接種) |

C型肝炎の潜伏期間は、感染からおよそ2~14週間とされています。感染したウイルスは自然に排除されることはなく、多くの人が自覚症状はないまま過ごし、慢性肝炎に進行するケースが多くみられます。
症状が出る場合には、倦怠感や食欲不振などがみられますが、これらは風邪などでもよくみられる症状のため、C型肝炎だと気づかず見過ごされることも少なくありません。
慢性肝炎のうち約30~40%は、20年ほどかけて肝硬変や肝がんへと進行するとされています。肝硬変になると、手のひらが赤くなる手掌紅斑や、皮膚や白目が黄色くなる黄疸のほか、むくみ、腹水、鼻血、出血傾向、腹痛、発熱などの症状があらわれることがあります。
C型肝炎の進行するスピードには個人差がありますが、高齢になるほど肝がんになるリスクが高まるため、自覚症状がない場合でも感染リスクがある方は早めに検査が重要です。

C型肝炎は、主にC型肝炎ウイルス(HCV)に汚染された血液が体内に入る「血液感染」によって感染します。日常生活での接触(食器の共有、握手、入浴、くしゃみなど)で感染することはなく、主な感染経路は以下のようなケースです。
1992年以前は、HCVを高い精度で検出する方法が確立されていなかったため、輸血や血液製剤からの感染が多く報告されていました。この時期に輸血や血液製剤の投与を受けた方は、自覚症状がなくても感染の可能性があるため、一度C型肝炎の検査を受けることが推奨されています。
過去の医療現場では、注射針の使い回しが行われていた時代があり、その際にウイルス感染が広がったと考えられています。現在、医療機関では注射針の使い捨てが徹底されていますが、覚せい剤などの薬物使用者間の注射器の共有などは、依然として問題になっています。
タトゥー(刺青)やピアス、鍼治療などで、適切に消毒されていない器具を使った場合にも、HCVに感染するリスクがあります。特に、無許可の施設で施術を受けた経験がある方は注意が必要です。
母親がHCVに感染している場合、まれに出産時に子どもへ感染する可能性があります。ただし、胎内での感染や授乳による感染は極めてまれであるとされています。
性行為や歯科治療などを介して感染するリスクは非常に低いと考えられていますが、HCVに感染した人の血液が付着した物が、傷口などを通じて体内に入ることで感染する可能性があります。

C型肝炎は、ほとんど症状があらわれないまま進行することが多いため、自覚症状がなくても感染の可能性がある方は、早めに検査を受けることが重要です。
まず行われるのが「HCV抗体検査」で、過去または現在にC型肝炎ウイルスに感染したことがあるかを調べます。この検査は、病気の初期段階で感染の有無をみつける「スクリーニング検査」と呼ばれ、まだ病気を発症していない段階で感染の有無を調べる目的で広く用いられています。
HCV抗体検査で陽性が確認された場合、その時点では過去の感染なのか、現在も体内にウイルスが残っているのかは判断できません。そのため、次に「HCV核酸増幅検査」を行い、ウイルスの遺伝子を検出することで、今も感染が続いているかどうかを確認します。
また、C型肝炎ウイルスには6つの遺伝子型(ジェノタイプ)があり、タイプによって治療法や効果が異なります。そのため、遺伝子型の特定も行われます。
あわせて、肝臓の炎症や障害の程度を確認するために、ALTやASTなどの肝機能の数値を調べる血液検査や、超音波検査、CT、MRIなどの画像検査が実施されることもあります。
現在、 C型肝炎の検査や治療にかかる医療費に対しては、自治体による公費助成制度が用意されています。医療費助成を活用することで、自己負担を抑えて治療を受けることが可能です。お住まいの地域の保健所や自治体のホームページなどで、最新の情報を確認しましょう。

C型肝炎の治療は、体内からウイルスを取り除く「抗ウイルス治療」が基本となります。以前は、「インターフェロン」という注射薬による治療が主流でしたが、日本人に多い遺伝子型(1型、2型)には効果が低く、副作用が多かったため、現在ではあまり使用されていません。代わって、インターフェロンを使わない治療法が一般的になっています。
抗ウイルス治療で使用される薬剤には、「インターフェロン」や「リバビリン」、「直接作用型抗ウイルス薬(DAA)」などがあります。
インターフェロンはウイルスの増殖を抑える注射薬で、かつては中心的な治療法でしたが、現在では使用頻度が減少しています。リバビリンは、他の薬剤と組み合わせて補助的に用いられる抗ウイルス薬です。
現在の標準治療は、直接作用型抗ウイルス薬(DAA)による内服治療です。DAAはウイルスに直接働きかけて増殖を抑え、高い確率でウイルスを排除できます。副作用が少なく、治療効果も高いため、DAAの普及によりC型肝炎の治療は大きく進歩しました。
C型肝炎ウイルスの排除が難しい場合や、肝がんのリスクが高いと判断された場合には、「肝庇護(かんひご)療法」と呼ばれる肝臓の炎症を抑える治療が行われることがあります。具体的には、ウルソデオキシコール酸やグリチルリチンを含む薬剤が用いられ、肝機能の改善を図ります。

直接作用型抗ウイルス薬(DAA)の登場によって、現在では多くの方でC型肝炎ウイルスを体内から排除することが可能になりました。過去にC型肝炎と診断されたものの治療を受けていない方、あるいはインターフェロン治療で十分な効果が得られなかった方も、現在の医療では高い確率でウイルスの排除が期待できます。
ただし、ウイルスが消えても、それまでに肝臓に蓄積したダメージは残ります。そのため、C型肝炎が治ったように見えても、肝がんのリスクは引き続き残る点に注意が必要です。治療後も定期的に検査を受け、肝臓の状態を確認することが重要です。
また、C型肝炎ウイルスは肝臓以外にも影響を与えることがあり、悪性リンパ腫、シェーグレン症候群、扁平苔癬、腎臓病、糖尿病などの疾患との関連性も指摘されています。
C型肝炎は自覚症状があらわれにくいため、気づかないうちに肝硬変や肝がんへと進行してしまうおそれがあります。しかし、早期に感染に気付き、適切な治療を受ければ、ウイルスを排除できる可能性が高くなっています。すでにC型肝炎と診断されている方にとっても、定期的に検査を受けることは肝がんの早期発見・予防に重要です。
近年は、がんのリスクを自宅で簡単に確認できる検査キットも登場し、注目を集めています。「サリバチェッカー」は、慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究に基づいて開発された検査キットで、唾液を採取するだけで複数のがんのリスクを一度に評価することができます。
唾液に含まれる微量な代謝物を、高感度の分析装置で測定し、 AIが複数のがんに対するリスクを総合的に評価します。こうした検査キットを取り入れることで、日常的に健康意識を高めることができ、病気の早期発見や予防につながります。