癌による腹水は、患者ご本人やご家族にとって深刻な問題です。お腹の膨満感や痛み、食欲不振などの症状が日常生活を大きく妨げます。さらに、「腹水が溜まると余命が短くなるのでは?」と不安を感じる方も多いでしょう。
本記事では、癌による腹水の特徴や原因、余命の目安、そして腹水を軽減する方法について詳しく解説します。腹水に関する正しい知識を得ることで、不安の軽減やより良い対策を講じられるでしょう。
目次
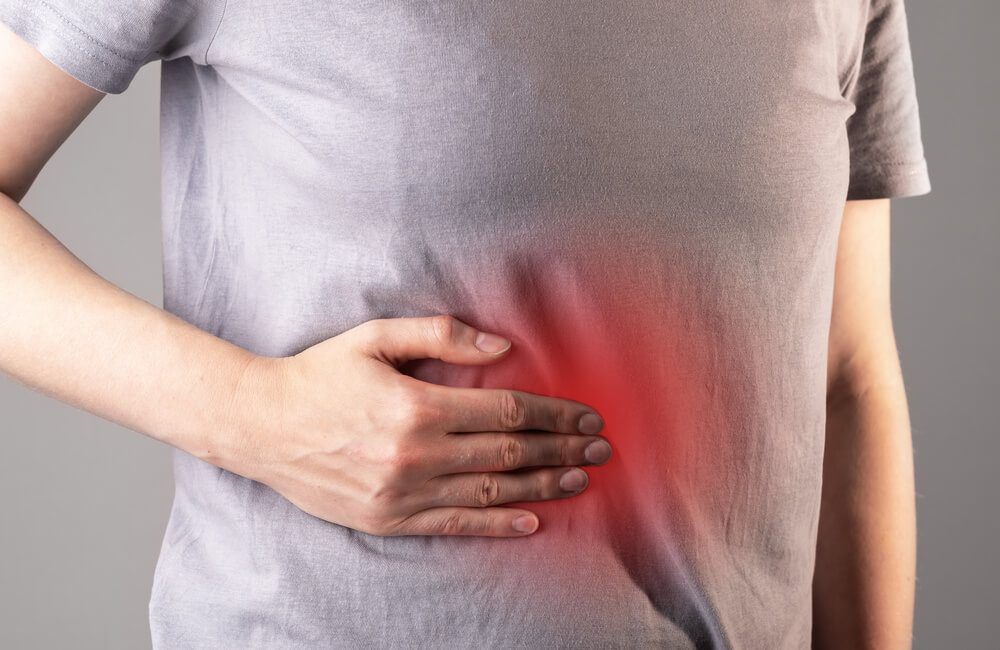
腹水とは、腹腔(おなかの中の空間)に体液が異常に溜まってしまった状態を指します。通常、腹腔内には少量の体液が存在していますが、これが過剰に増加すると「腹水」と呼ばれる状態になります。
通常の腹水は、ほぼ透明から淡い黄色の液体です。しかし、癌が腹膜(腹腔の内側を覆う膜)に広がり、出血を引き起こすと腹水の色が変化します。少量の出血であれば淡いピンク色になり、大量の出血が起こると真っ赤な色(血性腹水)になります。この血性腹水は癌に特徴的な所見で、医師はこれを診断の手がかりにすることもあります。
腹水の量も重要な指標です。少量であれば日常生活にほとんど影響しませんが、量が増えると腹部の膨満感や呼吸困難などの症状が現れます。癌の進行に伴い、腹水の量が増加することも少なくありません。
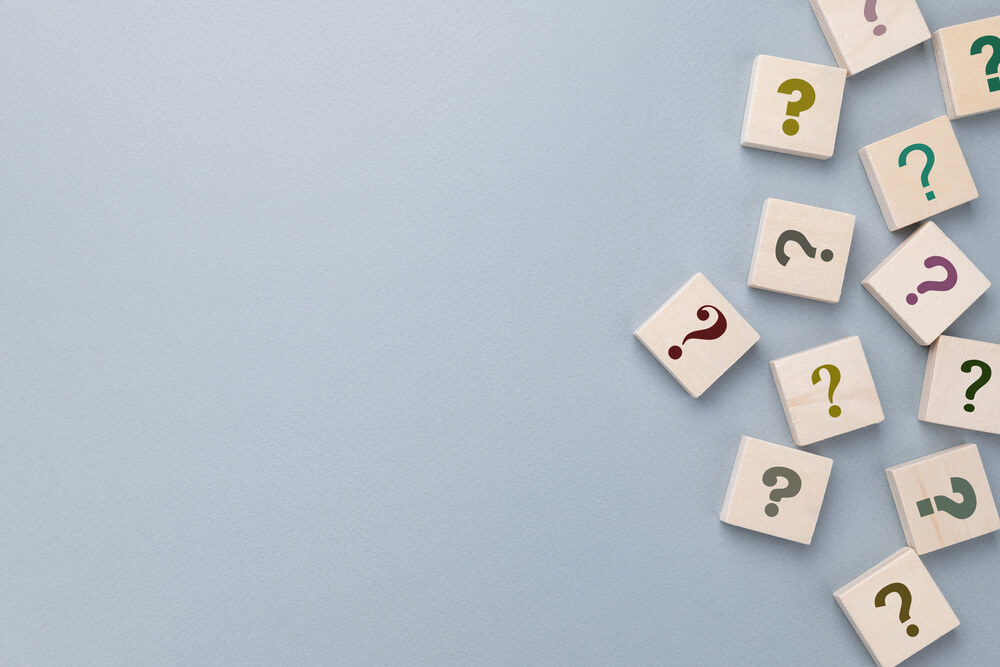
癌で腹水が溜まる原因にはいくつかのメカニズムがあります。腹水を伴いやすい癌の種類としては、卵巣癌、子宮体癌、乳癌、大腸癌、胃癌、膵臓癌などが挙げられます。これらの癌は腹腔内に広がりやすく、腹水を引き起こす可能性が高いといわれています。
腹水が発生するメカニズムは、主に以下の3つです。
それぞれ説明します。
「癌性腹膜炎」は、癌細胞が腹膜に広がり、炎症を引き起こす状態です。腹膜は腹腔内の臓器を包む薄い膜で、通常は体液の出入りを調整する役割を担っています。癌細胞が腹膜に広がると、腹膜の透過性が高まり、周囲から過剰な体液が漏れ出してしまうのです。
また、癌細胞自体も液体を産生するため、腹腔内に体液が溜まりやすくなります。腹膜全体に癌細胞が広がると、大量の腹水が発生することも。特に卵巣癌や胃癌では、この機序による腹水が多く見られます。
肝臓は、血液中のタンパク質の合成や、老廃物の解毒など、生命維持に欠かせない重要な役割を担っています。肝臓に癌が転移すると、これらの機能の機能を十分に果たすことができません。その結果、腹水が溜まってしまうケースがあります。
肝臓の機能が低下すると、血液中のアルブミンというタンパク質の量が減少します。アルブミンは血液中の水分を保持する役割があるため、減少すると水分が血管外に漏れ出して腹水となります。
また、肝臓の血流が阻害されて生じる門脈圧(肝臓に流れ込む血管の圧力)の上昇も、腹水の原因です。肝臓が原因の癌や、他の臓器からの肝転移がある場合、この機序による腹水が発生することがあります。
リンパ管の役割は、体内の余分な水分や老廃物を回収することです。癌によってリンパ管が圧迫されたり、詰まったりすると、リンパ液の流れが滞り、腹腔内に溜まることがあります。
特にリンパ節転移を伴う癌では、リンパの流れが阻害されることで腹水が発生しやすくなります。リンパ管の閉塞は、手術や癌の直接浸潤によっても起こりうるため、治療後の腹水に十分な注意が必要です。

腹水が溜まると、さまざまな身体的な不調が現れます。症状の種類や程度は、腹水の量や進行速度によって異なります。
腹水による主な症状には、以下のようなものがあります。
それぞれ説明します。
腹水による最も一般的な症状は腹部の膨満感です。腹部が膨らむことで、お腹の張りや胃や腹部の重苦しさを感じるようになります。
腹水が少量のうちは気づかないこともありますが、量が増えるにつれて腹囲(おなかの周り)が大きくなり、ズボンやスカートのウエストがきつくなるなどの変化が現れます。腹水の量が多くなると、立っているだけでも腹部に重みを感じ、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。
腹部の膨満感は、単なる不快感にとどまらず、患者さんの生活の質を大きく低下させる要因になりかねないため、早期からの適切な対応が重要です。
腹水が溜まると、腹痛を感じることもあります。水が溜まることで、お腹の内部に圧がかかり、胃や腸などの消化器官に影響を及ぼすためです。腹痛の程度や場所は人によって異なりますが、多くの場合、鈍い痛みや圧迫感として感じられます。腹水の量が急速に増加した場合に痛みを感じやすいでしょう。
適切な痛み止めの使用や、腹水を減らす治療によって、痛みの軽減が可能です。担当医に痛みの状況を詳しく伝えることが大切です。
腹水によって腹腔内のスペースが圧迫されると、胃や腸の動きが悪くなり、食欲不振につながります。少量の食事でもすぐにお腹がいっぱいになったように感じたり、食事に対する興味が減退したりするのがサインです。
食欲不振は単に食べる量が減るだけでなく、栄養状態の悪化や体力低下を引き起こすリスクがあります。癌患者さんにとって、適切な栄養摂取は治療を乗り切るための重要な要素であるため、早めの対処が必要です。
腹水による腹部圧迫は、胃の機能にも影響します。胃酸が逆流し、食道を刺激することで、吐き気や胸やけといった症状が現れることがあります。
特に横になった姿勢では、胃酸が逆流しやすくなるため、就寝時に症状が悪化することも少なくありません。枕を高くして上半身を少し起こした状態で寝ることで、症状が緩和するケースもあります。
腹水は腹部を膨張させた結果、胸郭と肺に向けて圧力をかけます。この圧力が高まると胸郭が圧迫され、肺の拡張が阻害されるため息苦しさを感じます。
また注意したいのが、腹水が溜まることで生じる息切れです。特に階段の昇り降りや歩行などの軽い運動でも息切れを感じることがあります。重度の呼吸困難は生活の質を著しく低下させるだけでなく、脳卒中や心筋梗塞などの他の健康問題を引き起こす可能性もあるため、早急なサポートを受けるようにしてください。
腹水によって下半身への血流が妨げられると、足にむくみ(浮腫)が生じることがあります。腹腔内の圧力上昇により、下肢からの静脈還流(血液が心臓に戻る流れ)が阻害されるためです。
むくみは、靴や靴下がきつく感じる、足首の周りが膨らむ、皮膚を指で押すとへこんだまま戻りにくいなどの症状として現れます。むくみが進行すると、歩行困難や皮膚トラブルのリスクも高まります。
足を少し高くして休む、適度な運動を行う、弾性ストッキングを着用するなどの対策が有効なこともありますが、根本的には腹水を改善することが重要です。

癌による腹水と余命の関係は、多くの患者さんやご家族が気にかける問題です。まず押さえておきたいのは、必ずしも腹水が癌の進行を決定づけるものではなく、余命は一概には言えないという点です。癌の種類、進行度、患者さんの全身状態、治療への反応など、さまざまな要素が影響します。
ただし、腹水は癌の進行に伴って現れることが多いため、一般的には予後(病気の見通し)にある程度の影響があるとされています。参考となる医学的なデータは、以下です。
卵巣癌で腹水が溜まる場合は、主にステージⅢ~Ⅳ期に該当する可能性が高いとされます。日本産科婦人科学会の報告によると、Ⅲ期の場合は5年生存率が45.1%、Ⅳ期の場合は5年生存率が27.8%です。ただし、治療法の進歩により、これらの数字は改善傾向にあります。
大腸癌の場合、腹水を伴う患者さんの平均生存期間は14.3~14.5か月という報告があります。しかし、個々の患者さんの状態や治療への反応によってはこの限りではありません。
胃癌の場合、腹膜播種を伴う進行例では、治療を行わない場合の平均生存期間が2~3か月という報告もありますが、近年の治療法の進歩により延長している傾向にあります。
これらの数字はあくまで統計的な平均値であり、個々の患者さんに当てはまるわけではありません。医療の進歩により、かつては予後不良とされていた状態でも、長期生存される方も増えています。最も大切なのは、担当医と十分に相談し、個々の状況に合わせた治療方針を決めることです。

腹水の治療法は、癌の種類や患者さんの全身状態によって異なりますが、主に5つの方法があります。腹水には栄養が含まれているため、一度に抜いてしまうと栄養状態が悪化し、体力が低下してしまうことがあるため、適切な治療法の選択が重要です。
それぞれ説明します。
塩分は体内に水分をためやすくする性質があるため、腹水がある場合は塩分制限が基本となります。塩分を摂りすぎると、利尿剤を使用していても効果が減弱してしまうことがあります。
一般的には1日の塩分摂取量を3~5g程度に制限することが推奨されます。具体的には、塩辛い食品や加工食品を避け、調理の際の塩分を控えめにするなどの工夫が必要です。
また、病状によっては摂取する水分量も制限されることがあります。通常、1日1.5~2リットル程度の水分摂取が推奨されますが、腹水が多い場合は1リットル程度に制限されることもあります。
食事療法の利点は、薬物や侵襲的な処置を行わずに腹水をコントロールできる可能性がある点です。一方で、食事制限による栄養不足や、食欲低下による体力低下などのリスクもあります。栄養士と相談しながら、栄養バランスの取れた食事計画を立てることが重要です。
利尿薬は、余分な水分を尿として排出しやすくする薬剤です。腹水の治療では、スピロノラクトン(アルダクトンA®)やフロセミド(ラシックス®)などがよく使用されます。こ薬剤は腎臓に作用し、ナトリウムや水分の再吸収を抑制することで尿量を増やし、体内の余分な水分を排出します。利尿薬による治療は、比較的軽度の腹水に対して効果的です。
利尿薬の利点は、非侵襲的で日常生活への影響が少ない点です。しかし、電解質異常(特にカリウム値の変動)や脱水、腎機能障害などの副作用にも注意が必要です。定期的な血液検査で、電解質のバランスや腎機能をチェックしながら使用することが重要です。
腹水が癌によるものであれば、腫瘍の縮小を目指して抗癌剤治療が行われることがあります。癌細胞を直接攻撃することで、腹水の原因となっている癌の活動を抑制するのが目的です。抗癌剤の種類や投与方法は、癌の種類や患者さんの状態によって異なり、腹腔内に直接抗癌剤を投与する腹腔内化学療法が選択されることもあります。
抗癌剤治療の利点は、癌自体に対する治療と腹水の改善を同時に目指せる点です。しかし、副作用や体力低下のリスクもあるため、患者さんの全身状態を慎重に評価した上で適用を決める必要があります。
腹腔穿刺ドレナージは、腹腔内に細い針を刺して腹水を体外に排出させる治療法です。多量の腹水により強い腹部膨満感や呼吸困難がある場合に、速やかな症状改善を目的として行われます。
手技自体は比較的簡単で、局所麻酔下で実施されます。腹腔穿刺の利点は、即効性がある点で、処置後すぐに腹部の膨満感や呼吸困難が改善されることが多いです。一方で、一時的な処置であり、根本的な解決にはならないこと、低タンパク血症や感染のリスクがある点がデメリットです。また、短期間に大量の腹水を排出すると栄養状態が悪化する可能性もあります。そのため、一度に排出する量や頻度には注意が必要です。
CARTは、抜いた腹水から水分を取り除いて濃縮し、タンパク質など有用な成分を点滴として体に戻す治療法です。腹腔穿刺で排出した腹水を特殊なフィルターにかけ、癌細胞や細菌を除去した後、濃縮して静脈内に戻します。そのため、腹水に含まれるタンパク質などの栄養成分を体内に戻すことができます。
CARTの利点は、腹水を排出しながらも栄養成分の損失を最小限に抑えられる点です。特に低タンパク血症がある患者さんには有効な方法です。デメリットとしては、設備や専門技術が必要なこと、発熱などの副反応が起こる可能性がある点が挙げられます。
腹腔静脈シャントは、大量の腹水を短期間で減少させるのに効果的な方法の一つです。細長いチューブ(カテーテル)をお腹の中と静脈につなぎ、溜まった水を血液の中に戻します。食事制限や利尿剤を使っても改善されない方に適応されることがあります。
腹腔静脈シャントの利点は、お腹まわりの張りが軽減され、呼吸や食事が楽になる点や入院期間を短縮できる点です。一方で、チューブの詰まりや感染、肺塞栓などの合併症リスクがあること、癌細胞が血流に入る可能性がある点がデメリットです。
癌による腹水は、患者さんの生活の質に大きな影響を与える症状です。腹水が溜まる主な原因は、癌性腹膜炎、肝転移、リンパ管の損傷や閉塞などがあります。
大切なのは、腹水が溜まる前に癌を早期発見し、治療するという観点です。手軽に癌リスクを調べる手段として、「サリバチェッカー」という検査キットがあります。
腹水と余命の関係については、癌の種類や進行度、患者さんの状態によって大きく異なります。統計的なデータはあくまで参考値であり、個々の患者さんに当てはまるわけではありません。医療機関ではもちろん、個人でも購入できるため、気になる方はぜひ一度、チェックしてみてください。
癌の治療は日々進歩しており、以前は対応が難しかった腹水に対しても、より効果的な治療法が開発されています。担当医と十分に相談し、個々の状況に合わせた治療方針を決めることで、症状の緩和と生活の質の向上を目指しましょう。